
桜田門外の変とは?
今から約160年前、東京の霞が関で日本全国を揺るがす暗殺事件が起きたのをご存じだろうか?
当時は幕末の日本、アメリカ人ペリーが黒船を率いて浦賀港に来航し、日本全国のサムライ達が奮闘した時代である。坂本龍馬や西郷隆盛、新選組など、幕末ファンは多いだろう。
黒船来航から7年後に起きたこの事件「桜田門外の変」を紐解いていきたい。
桜田門外の変は、安政7年(1860年)に江戸城桜田門外(現在の東京都千代田区霞が関)で起きた事件だ。この事件では、水戸藩からの脱藩者17名と薩摩藩士1名が彦根藩の行列を襲撃し、大老(徳川将軍を補佐する最高職)・井伊直弼を暗殺した。この事件は「桜田事変」とも呼ばれている。

井伊家は赤備えに由来する名家
井伊直弼は井伊家の出身であり、赤備えとして知られる名家だった。彼は幕末の重要な政治家であり、その死は幕府の終焉につながるきっかけとなったと言っていいだろう。
戦国時代、徳川家康の精鋭部隊であった井伊直政は、赤備えの鎧を付けて活躍した。赤い鎧は当時の戦闘において、相手を威圧し味方の戦意を高めるのに役立ったと言われる。井伊直政以外にも、武田信玄の家臣・山県昌景や真田幸村も赤備えの軍団を率いたことで有名だ。
現在でも、居酒屋や飲食店の看板には赤色が多い。これは、赤は食欲を掻き立てる色としてデータがあるらしい。
食に関わらず、カラーが心理に与える影響を戦いの場で活用することは、極めて実用的で科学的だと言っていいだろう。
井伊直弼の死を伏せた理由
井伊直弼が「桜田門外の変」で暗殺された後、井伊家家臣達は主君の死を伏せたと言われる。徳川幕府NO.2の権力者の死を伏せる理由、それは恥を隠す意味では無く、他にあった。
当時の徳川幕府政権では、主君が跡継ぎを決めないで死んだ場合、お家断絶(国である藩が取り潰しになること)というルールがあったらしい。
井伊家・家臣は、自分たちの国を守るために、必死のウソをついていたのだ。主君の突然の死を受けて、国を守るために試行錯誤した家臣団を想像すると、敬意を感じずにはいられない。
現代ビジネスの場において、急にCEOの退任が決まったシーンを想像してみて欲しい・・。
「誰が後任か」「取引先への連絡と関係維持はどうしよう」「社員たちへの説明はいつ行うか」考えただけで、混乱せずにはいられない。
日米修好通商条約
日米修好通商条約は、日本とアメリカが結んだ貿易や開港に関する条約だ。
井伊直弼は、天皇の許しを得ずにこの条約を結んだため、多くの批判を集めることとなる。アメリカの総領事(外交官)ハリスは、幕府に条約を受け入れるよう迫っていた。しかし、幕府は孝明天皇に条約の調印を許可するよう求めたが、すぐに許可は出なかった。
そこで井伊直弼は独断での条約締結に踏み切ったのだ。この天皇の意思を無視した調印は、尊皇派・攘夷派から大バッシングを受け、一部の志士(幕末のサムライ)たちに火をつけることとなった。
また、日米修好通商条約が日本にとって不利な不平等条約だったことも批判に拍車をかけた。
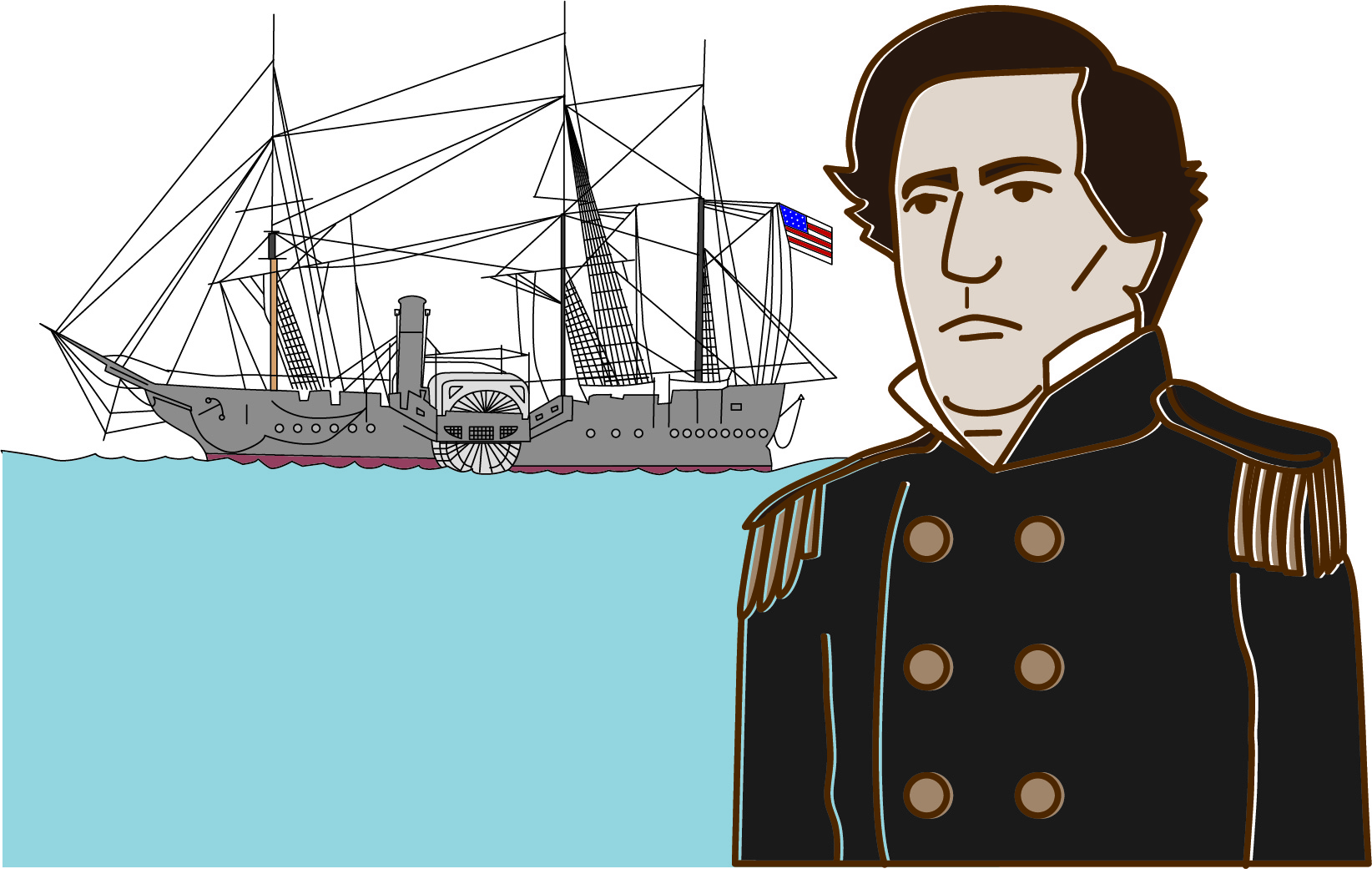
14代将軍の選定
当時の将軍は13代の徳川家定であった。家定は病弱で子供が望めなかったため、後継者として養子が必要となり、14代将軍候補には一橋慶喜(後の15代将軍)と、家定の従弟にあたる徳川慶福(家茂)の名前が挙がった。
後継者を巡って幕府内で対立が起こる中、井伊直弼は大老に就任し血筋を重視して慶福を推し、次期将軍の座につかせた。この強引な選定に対して、水戸藩主・徳川斉昭らは直接江戸城に出向いて井伊直弼を非難したと言われる。江戸城は本来、登城日を外れての登城を許さない場所であり、斉昭らは政界から追放されることとなった。
そう、桜田門外の変は水戸脱藩浪士が中心となって起こした事件であり、背景として水戸藩主追放が影響していることが想像される。
<PR>
安政の大獄
大老・井伊直弼の決断
徳川慶福が家茂と名を改めて14代将軍となり、日米修好通商条約が結ばれたころ、孝明天皇は水戸藩に手紙を送った。この手紙は幕府の勝手への批判と、攘夷(外敵を撃ち払って入国させない、幕末の外国人排斥運動)を進めたいという内容であった。
戊午の密勅(ぼごのみっちょく)とも言われる。天皇が幕府を通さず直接、藩に意見を伝えることは異例であり、これによって水戸藩は攘夷派の拠点となったのだ。
井伊直弼は、日米修好通商条約に調印と将軍継嗣決定問題への反対が起きた状況を重く受け止め、幕府の存続を守るために苦肉の策を講じた。これらの諸策に反対する者たちを弾圧したのである。「安政の大獄」と言われるこの事件で弾圧されたのは、尊王攘夷や一橋派の大名・公卿・志士(活動家)らで、連座した者は100人以上にのぼったと言われる。長州藩(現在の山口県)の吉田松陰も、この事件で命を落とした一人である。
形式上は13代将軍・徳川家定が台命(将軍の命令)を発して全ての処罰を行なったことになっているが、実際には井伊直弼が全ての命令を発したと言われる。
「桜田門外の変」は、幕末の志士や藩士たちが組織を守るために取った行動の一つであり、その背後には様々な苦悩と決断があったことを理解することが重要だ。それぞれの事件や行動には理由があり、視点が異なる人同士がぶつかり合った結果である。歴史の中での葛藤や選択は、私たちが組織を築く際にも参考になることが多い。
幕末の忠臣蔵を防ぐ
江戸幕府が井伊直弼の死を隠そうとした理由として、幕末の「忠臣蔵」を防ぐ意味合いもあったらしい。
「忠臣蔵」とは、江戸時代中期の元禄期に発生した事件で、吉良上野介を討ち損じて切腹に処せられた浅野内匠頭の代わりに、その家臣である大石内蔵助以下47人が、吉良を討ったものである。「赤穂事件」とも言われる。
もし、井伊直弼の死で彦根藩が取り潰しとなった場合、桜田門外の変で主君を失った彦根藩家臣たちが仇討ちを行うことを事前に避けるための決断だったのだ。
組織継続への苦肉の策
桜田門外の変で井伊直弼が暗殺されたことで、江戸幕府の組織が大きく揺れ動いた。井伊直弼の死は、彦根藩や他の藩士たちにとっても大きな衝撃であり、組織の存続を守るためには苦渋の決断が必要であった。彦根藩は主君の死を伏せ、組織を継続させるために様々な策を講じたのである。
このような苦肉の策は、組織を守るためには避けられないものであり、その背後には多くの葛藤があったことを理解することが重要だ。
平和を願う家臣たちの苦悩(彦根藩30万石)
井伊直弼の死を知った際、彦根藩家臣は30万石の国と領地を守る立場にあった。家臣たちは平和を願いつつも、組織の存続を考える苦悩に直面していただろう。
桜田門外の変は、幕府の体制を揺るがし倒幕のきっかけとなった大事件として実行者側(水戸脱藩浪士)をフォーカスしがちだが、その背景で彦根藩を守るために苦悩していた家臣団も忘れてはいけない。
<PR>
大政奉還・時代が変わった瞬間

徳川斉昭の突然の病死
事件の後、徳川斉昭が突然病死した。14代将軍家茂も亡くなり、水戸藩出身の徳川慶喜が15代将軍となる。
家茂は若干21歳で亡くなり、皇女和宮と結婚した(和宮降嫁)でも有名だ。しかし、その若さで亡くなったことは、多くの人々に衝撃を与えたと言われる。
これにより、幕府の組織構築に大きな影響を及ぼすこととなる。桜田門外の変で幕府最高職の井伊直弼を暗殺したのは水戸脱藩浪士で、その後15代将軍となる徳川慶喜もまた水戸藩出身である。幕末動乱期における時代の流れと、因縁を感じずにはいられない。
大政奉還
1867年(慶応3年)江戸幕府15代将軍・徳川慶喜は、京都二条城で政権返上を明治天皇へ奏上した。大政奉還(たいせいほうかん)である。
徳川家康が幕府を開いて約260年、政権を天皇に返上したことで実質徳川幕府は終わりを迎えることとなる。
大政奉還の目的は、内戦を回避しつつ、幕府独裁制を修正し、徳川宗家を筆頭とする諸侯らによる公議政体体制を樹立することにあったとも言われる。しかし、大政奉還後に想定された諸侯会同が実現しない間に、薩摩藩を中核とする討幕派によるクーデターが起こったのである。
結果として臨む方向に進まなかったが、大政奉還は時代の流れを変えた徳川慶喜の英断と言えるだろう。
「桜田門外の変」は、幕末の志士や藩士たちが組織を守るために取った行動の一つであり、その背後には様々な苦悩と決断があったことを理解することが重要だ。
そして、日本全国の幕末の志士に衝撃を与え、時代が動くきっかけとなったと言っていいだろう。歴史の中での葛藤や選択は、私たちが組織を築く際にも参考になることが多く、学ぶべき点は多い。